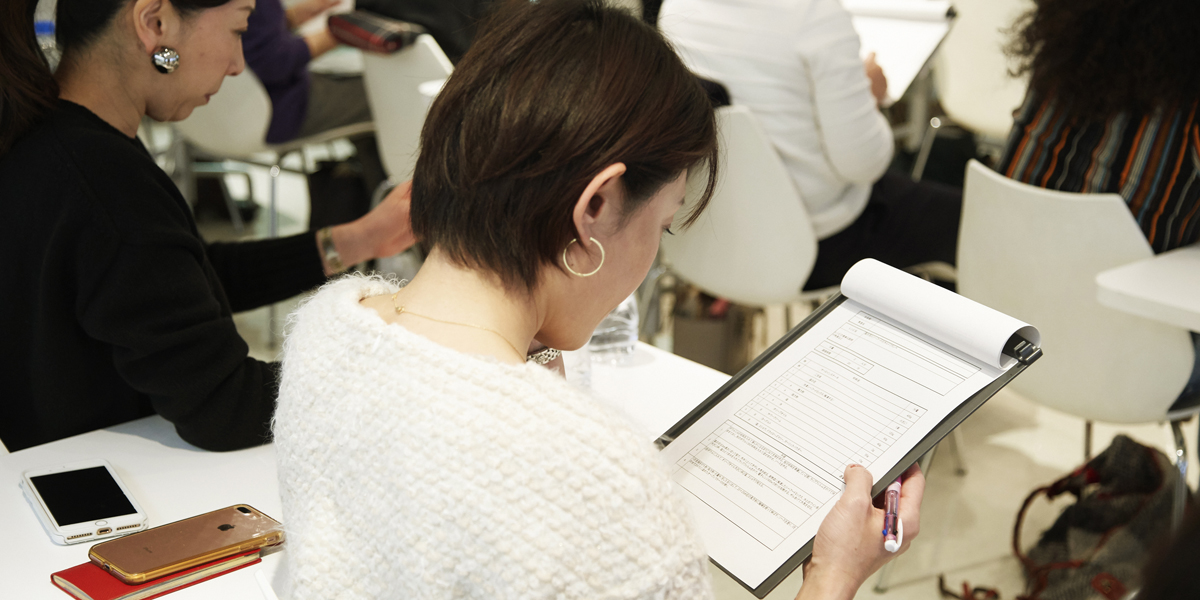反対に、悪いレシピとは「説明が不明瞭」「難しい専門用語が頻出する」「初心者なのか上級者なのかなど、誰に向けて作られたものかがわからない」などといった例が挙げられ、これまでレシピを書いたことがある人ならドキリとするような内容も。さらに、「材料名には記載があるのに、工程の説明に最後までその食材が出てこなかったり、分量が間違っていたりなど、ちょっとしたケアレスミスのために正しく作れないレシピって意外と多いんです」と宇多さん。わかりやすいレシピを目指すと同時に、矛盾や誤りのないレシピを書くことも重要だと、教えてくれました。

良いレシピを書くコツを一通り披露した後には、『エル・グルメ』の公認料理家組織、「エル・グルメ フードクリエイター部」で活躍する料理家から提出された実際のレシピの公開添削が行われました。「材料名を書く欄の中で、“大さじ・小さじ”による表記があるかと思えば、その下の食材が“グラム表記”だったり、単位の混在は誤解を生みやすい」「液体の分量表示は、ccでもmlでもどちらでも構わないが、統一させることが大事」など、思わずハッとするような指摘の数々に、自分自身も普段、何気なく同じ過ちをしていることに気づいたという参加者も。
続く質疑応答の時間には、「料理名はどうやってつけるのが正解?」「予熱が必要な場合、どの段階でどのように表記するのがわかりやすいか」「レシピの総調理時間には、漬け込んだり固めたりといった作業時間も加えるべき?」「1つの料理で同じ調味料を2回使うときは、材料欄にはどう書いたらいい?」など、わかっているようで表記が難しい事項について数々の疑問がぶつけられ、レシピ制作の奥深さを痛感することに。
「レシピの書き方は、媒体によってもルールが違いますし、一概にこれが正しいということは言えない。それが難しいところなんです。けれど、料理を作る人が、作り始めてから仕上げまでの間に困惑しないよう配慮してレシピを書くことが、何よりも大事。皆さんも、自分でルールを決めて書くのがよいでしょう。教室なら生徒の立場を考え、企業との仕事であればクライアント目線を意識するなど、誰に向けて作るかを決めてレシピ制作に当たるとブレません。また、料理専門の媒体や著名な料理家などによって書かれた、いわゆる“いいレシピ”をたくさん見るのもおすすめ。我々編集部のスタッフも、今でもいろんな雑誌や料理家のレシピを見て勉強を重ねる日々です」