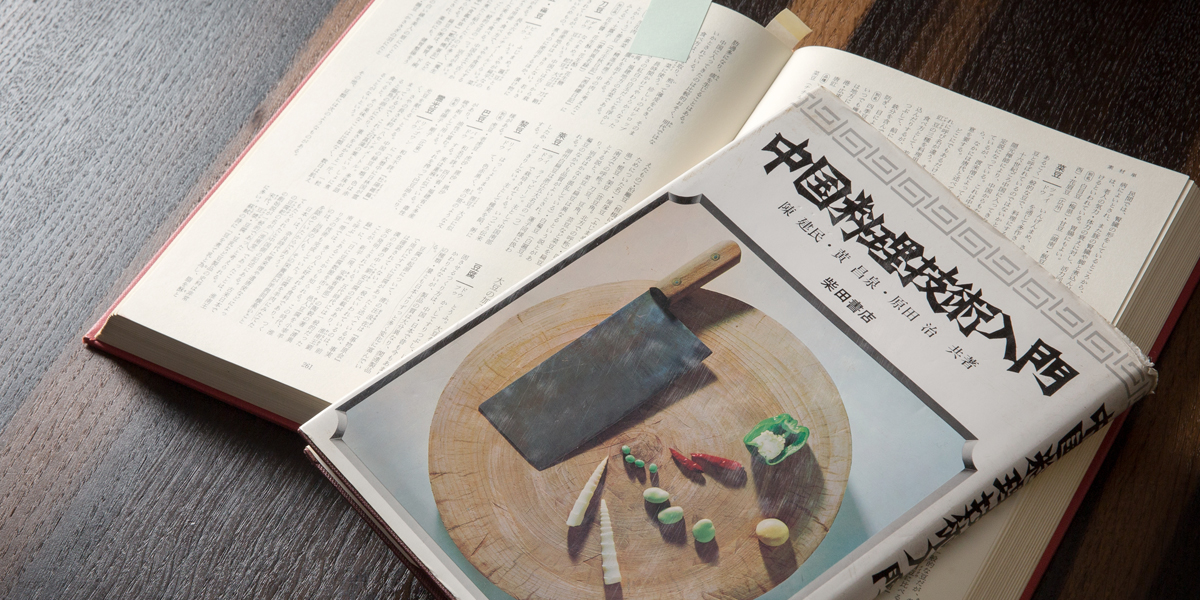44歳で薬膳を学び、中国の国家資格を取ったわけ

菰田さんを中国料理界のトップに押し上げたのが、この「継続する力」です。料理人としてキャリアをスタートした頃から、四川飯店グループ全体の総料理長として目まぐるしい毎日を過ごし、自身の拠点を構えた今現在まで、一年に1、2度はなんとか時間を捻出し、中国の四川省を訪れています。旅の目的は、食べ歩きと食材の仕入れとか。「料理の世界は日々進化していますから、現地を訪れると、やっぱり気づきや学びがあるんですね。30年通い続けても、新しい発見があります」
44歳のときには、すでに四川飯店グループの取締役総料理長という地位を手に入れ大活躍していたにもかかわらず、忙しい中で中国薬膳の勉強を始め、国家資格を取得しました。「薬膳料理は身体にいいけれどおいしくない。そんな漠然とした印象は正しいものなのか。きちんと学ばずにイメージだけで否定するのは、料理人としておかしいのではないかと気づいたことがきっかけでした」
薬膳について知識を得た今は、自身で生薬を配合したスープなどもメニューに取り入れているそうです。
「そんな褒めていただくようなことではないですよ。今日よりも明日、ちょっとでもおいしい料理を作れるようになりたい。毎日そう思っていたら、あっという間に30年以上が経っただけです」。あくまでも謙虚な姿勢が菰田さんらしい。
独立後、皿洗いの現場から見えたこと

四川飯店グループの取締役総料理長として駆け抜ける毎日のなかで、50歳を前にして、菰田さんの気持ちに変化が訪れます。四川飯店グループ全体をまとめる総料理長ですから、毎日お迎えするたくさんのお客様の数のコントロール、食材の仕入れや売上の計算など、その業務は膨大なものでした。
「大きな仕事を任せてもらったことは、すごくありがたかったですし、やりがいがありました。けれども料理人として、もっと料理自体に向き合いたくなったのです。僕は、料理とは、その土地の気候風土を、料理人を通して表現するものだと考えています。グループの総料理長としては、四川飯店の看板がありますから、それを外すわけにはいきません。50歳を前に、最後は看板を外した自分自身を、料理で表現したくなりました」

まさに機が熟した独立です。最初にオープンしたのは、これまでの職場であるホテルの高級中国料理店とはまったく異なる、カジュアルな火鍋専門店「ファイヤーホール4000」でした。オープン直後から1ヶ月間、菰田さんはここで洗い場やホールでの接客を担当していたそうです。
「大人数を抱えた組織では、仕事を分担し、自分ではやらない作業も多くありました。組織の長として高くなっていた目線を、一度ステージを降りてリセットすること。お客様に直接お会いすることで、街の雰囲気や世の中の流れを直接感じることが目的です」
洗い場では、お客様が残されたものから好みを知るなど、新しい発見も多かったとか。ここで新しい火鍋のスタイルを作り上げつつ、一年以上かけてじっくりと「4000チャイニーズレストラン」の開店準備に取り組みました。
先が見えない料理人に、働きやすい仕事場を提供したい

現在は変動的な営業日で、休日も多く取り、夜はお客様の入れ替えをせず1回転のみなど、ひと組ずつのお客様と丁寧に向き合うことを大切にしている菰田さん。ここでは素材をとことん突き詰め、四川料理をベースにした「いまの東京の味」を作り出したいと言います。「商売なので売り上げはもちろん大切ですが、レストランが大切にするべきことは、利益の追求だけではありません。どんな料理とおもてなしを提供すればお客様に喜んでいただけるか。笑顔で楽しんでいただけるかを、常に考えて進化したいですね」
そんな菰田さんがお客様と同じくらい大切にしているのが、共に働く従業員たちです。「中国料理の世界は厳しく、料理人を目指す若い人は少ないのが現状です。これからは、将来が不安定で先が見通しにくいといわれる料理人のイメージを変え、若い人たちを育てることを大切にしていきます」
今は事務作業もすべて自分でこなし、お金の流れをすべて把握して、よりよい組織を作るためにビジネス書を読むなど、学びを継続しているとか。福利厚生のひとつとして、若い人に楽しんでもらおうと、昨年は社員旅行で福島県へ、今年は3日間の台湾旅行を計画しています。
「中国の考え方で12年をひと回りとすると、48歳で独立して60歳までがひと回りです。それまでは全力を尽くします」と菰田さん。菰田さんの学びの日々は、いまも継続中です。