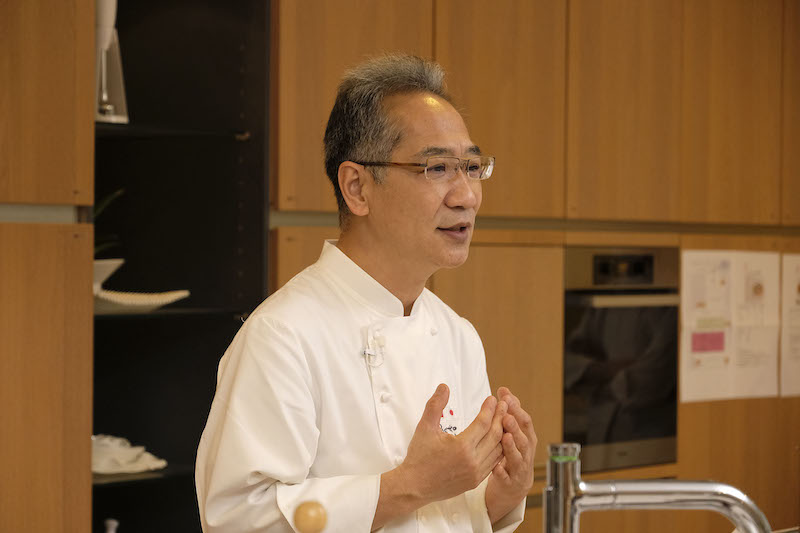「野菜が映える器だね」のひと言が転機
陶芸の一通りの基礎を学び指導所を卒業したKeicondoさんは、JICAの海外派遣の募集に応募し2年間、陶器の技術指導のため南米ボリビアにわたります。そして28歳で帰国したKeicondoさんは、笠間に帰り工房を開くのです。「誰かに教わることで、自分の色をなくしたくない」と、師匠に弟子入りすることなく、独立しました。
しかし、コネクションも実績もないKeicondoさんにすぐに注文が来たわけではありません。1年は、まったく売れませんでした。「器は白がいい、黄色の器なんて受け入れられるはずがない」というような意見もあり、方向性に迷いも生まれます。そんななか、Keicondoさんを支えたのは、笠間の陶器市で出会ったある料理家の言葉でした。
笠間の陶器市「陶炎祭(ひまつり)」は、期間中の来場者が50万人を超す大きなイベントです。その陶器市に独立2年目で出店したKeicondoさんの器を手にし「この器はいい、野菜がきっと映えるよ」と気に入ってくれたのが、菜園料理研究家の藤田承紀さんでした。
![]()
できる限り笠間のアトリエに来てもらい、直接コミュニケーションを重ねながら、その食卓にあう器を選び、作っていきたいとKeicondoさん。
「うれしかったですね。それから『料理と器は面白い』と思い、料理が映える器、料理を支える器をつくっていこうと決めたのです」。独立して2年、使ってもらう人が誰なのかがしっかりと定まったことで迷いが消え、制作に集中することができるようになります。すると自然と完成する器もまとまっていくようになります。
素材が映える器でありたい
「忙しい家庭でも、たとえば昨晩の残りものをさっと器にもっただけでおいしそうに見える。きちんと料理をしなくても、ゆでただけの野菜や焼き魚でも、素材が映えるような器を作りたいです」。それが、Keicondoさんが目指す器です。
「あくまで料理がメイン、器に盛ることで料理がよく見える、素材がよく見えるようになるのが一番いいと思っています。色だって僕じゃなくても表現できるし、形も特別なものはない。じゃあ、あえて僕らしさは何かと考えると、料理が主役だと考えているところ。それが独自性になったのかな。これがThis is keiだ!なんて、作家の僕の顔が見えちゃう器で料理を食べたくないじゃないですか(笑)。僕は、器で料理を支えたいんです」
![]()
将来的には、Keicondoの器を海外にも持っていきたいという。今、好んで作っているのがシンプルなプレートやボウル。日本的なものよりも、どこの世界にいっても使いやすいものに今は惹かれているといいます。
だからこそ、器をつくるなら使う側の意見に積極的に耳を傾けたいとKeicondoさんは考えます。試作ができあがれば、常磐線に飛び乗り、2時間かけて都内のレストランに持参し、感想を直に聞くことも多いそうです。「料理が盛られた器の美しさをよく知っているのは、食のプロの方々です。そういった方とのコミュニケーションのなかから、お互いがよいと思ったり、楽しいものを見つけることを大切にしたいんです」とKeicondoさん。電話やメールになることもありますが、できるだけ人と会って話すことを大切にしています。
「イベントをして気に入ってもらえて『器置いて行ってくれないかな』とか、使ってくれているお店に来た別のお店が気に入ってくれて、『紹介してもらった』といって、連絡をくれたり。自分で使ってみて、ほかの方にも勧めてくれる方が多くて、それは最高の誉め言葉だなって思っています。それに、毎日使ってくれる人の意見の方が大切だと思っています。器がコミュニケーションのツールになれば、本当に幸せですね」